Web制作には、以下の2つの方法があります。
- 自社内で制作する
- 外部に委託する
外部に委託する方法について詳しくみていきましょう。
Webサイトの制作を外部に委託する場合は、専門知識と経験を持つ制作会社やフリーランスのデザイナー・エンジニアに任せます。
自社に専門スタッフがいない場合や、大規模なWebサイトを短期間で立ち上げる必要がある場合に適しています。
委託先の選定には、制作会社の実績や評判、予算とのマッチングを慎重に行う必要があります。
また、制作の進捗状況を定期的に確認し、コミュニケーションを密にとることが重要です。
外部委託のメリットとして、高品質なWebサイトを効率的に制作できる点が挙げられます。一方で、コストがかかることや、自社の意向が完全に反映されない可能性があることは留意しておく必要があります。
Web制作外注の基本的な流れ
事前準備が終わり、Web制作を外注する際には、主に以下のような流れで進みます。
選定・契約フェーズ
- お問い合せ
- ヒアリング
- 企画提案・見積
- 申込・契約
制作フェーズ
- 企画・サイト設計
- デザイン制作
- 実装
- 公開・保守・運用
ホームページの作成プロセスは、制作会社の選択や契約を行う「選定・契約フェーズ」と、企画やサイトの設計から公開に至るまでの「制作フェーズ」の2つの段階に区分されます。
これらの各ステップについて、詳しく解説していきます。
選定・契約フェーズ
最初のお問い合せの段階では、プロジェクトに関する疑問や要望を提出します。
製作会社には、デザインに特化したところやシステム開発を得意とする企業など、それぞれに特徴があります。
各社の得意分野を確認し、気になる数社に見積もりを依頼してみるとよいでしょう。
次のヒアリングはWeb制作の初期段階で最も重要なプロセスのひとつです。
この段階では、Web制作の目標、期待するサイトの機能やデザイン、予算などについて明確に制作会社に伝えましょう。ヒアリングのうえ、納得できる制作会社を選定できたら、最後に申込をします。
制作フェーズ
企画・サイト設計段階では、サイトの構造やページのレイアウトを検討し、ユーザビリティを高めるための設計を行います。
デザイン制作の段階では、Webサイトのビジュアル面が形作ります。
サイトのレイアウト、色彩、フォントなどの基本的なデザイン要素を決定しましょう。
制作会社にフィードバックを行いながら、デザインを繰り返し改善し、最終的なデザインを完成させます。
実装フェーズでは、デザインを実際のWebサイトとして機能させるためのコーディング作業が行われます。HTML、CSS、JavaScriptなどの言語を使用して、デザインカンプを基にページのレイアウトや動作を実現します。
そしてWebサイトの公開後は、保守・運用が重要です。
これには、定期的なコンテンツの更新、セキュリティパッチの適用、バックアップの取得などが含まれます。
また、ユーザーからのフィードバックを受けて、サイトの改善を継続的に行うことも大切です。サイトのアクセス解析を行い、訪問者の行動を分析することで、よりユーザーフレンドリーなサイトにしていきましょう。
Web制作に必要な納期
Web制作における納期は、プロジェクトの規模や複雑さによって大きく異なります。
一般的に、シンプルなWebサイトであれば1〜2ヶ月程度、大規模で複雑なWebサイトの場合は3〜6ヶ月以上の納期が必要となることがあります。
制作会社との連携や承認プロセスにも時間がかかることを考慮し、余裕を持った納期設定が大切です。
適切な納期管理により、高品質なWebサイトを実現できるでしょう。

Web制作会社を選ぶときのポイント
実績や経験
Web制作会社を選ぶ際、実績や経験は重要な要素です。
多くの優れたWebサイトを制作してきた実績のある会社は、高い技術力とノウハウを持っているでしょう。
また、さまざまな業種や規模の企業との取引経験が豊富な会社は、クライアントのニーズを的確に理解し、適切なソリューションを提供できると期待できます。
会社の実績を確認する際は、ポートフォリオをチェックし、デザインの質、ユーザビリティ、機能性などを確認しましょう。加えて、クライアントの満足度や、プロジェクトの規模や複雑さにも注目します。
コスト
Web制作会社を選ぶ際、コストは重要なポイントです。
予算に合った会社を選ぶことで、プロジェクトを円滑に進められます。
ただし、安すぎる見積もりには注意が必要です。
品質の低下や追加料金のリスクがあるためです。一方、高すぎる見積もりも避けるべきです。
適正価格で品質の高いサービスを提供する会社を選びましょう。
運用システムやセキュリティ
Web制作会社選びで重要なのは、運用システムやセキュリティ面の充実度です。
自社でサーバー管理やセキュリティ対策を行える体制が整っているかを確認しましょう。
また、CMSの種類や使いやすさ、バックアップ体制なども要チェックです。
セキュリティ面では、SSL対応やウイルス対策、不正アクセス防止策などを講じているか確認が必要です。安心して任せられる会社を選ぶためには、運用面とセキュリティ面の両方を満たしていることが大切です。
アフターサポートや保守体制
アフターサポートや保守体制は、Webサイトを長期的に維持・運営していくうえで重要な要素です。
制作会社によって、サポートの内容や期間、費用などが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
具体的には、サイト公開後のトラブルへの対応方法や、更新作業の代行サービスの有無、セキュリティ対策やシステムのアップデートなどについて、詳しく説明してもらいましょう。サポート体制が手厚く、迅速な対応が期待できる会社を選ぶことで、安心してWebサイトを運用できます。
コミュニケーションのとりやすさ
Web制作会社を選ぶ際、コミュニケーションのとりやすさは重要なポイントです。
プロジェクトの進行中、疑問や変更点が生じた際にスムーズに連絡が取れるかどうかはプロジェクトの進行や完成度に影響します。担当者との相性や、質問への回答の速さ、説明のわかりやすさなどを確認しましょう。

Web制作依頼ならWebま!へお問い合わせを
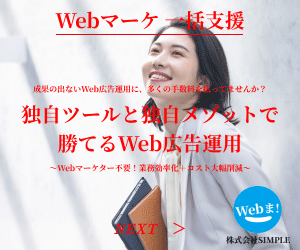
お問い合わせはこちら⇒https://webma.co.jp/
Web制作の種類
コーポレートサイト
コーポレートサイトは、企業の公式情報を発信し、ブランドイメージを構築するためのWebサイトです。
会社概要、事業内容、経営理念、沿革、IR情報などを掲載し、ステークホルダーに向けて企業の姿勢や価値観を伝えます。
また、採用情報や問い合わせ先なども記載し、求職者や顧客とのコミュニケーションを促進します。
コーポレートサイトは、企業の顔となるWebサイトであり、信頼性や専門性を感じさせるデザインが求められます。
サービスサイト
サービスサイトは、企業や個人が提供するサービスの紹介に特化したWebサイトです。
サービスの内容や特徴、料金体系、利用方法などを分かりやすく説明することが重要です。
サービスサイトを運用することで、製品を求めてサイトを訪れるユーザーに対して、一日中いつでもアプローチできます。
コーポレートサイトでは伝えきれない詳細な情報や、その業界に特有の内容を発信することで、より効果的な成果を期待できます。
オウンドメディア
オウンドメディアとは、企業や個人が自ら情報発信するために運営するWebサイトやブログ、SNSアカウントのことです。
オウンドメディアの運営は、ブランディングの強化、新規顧客獲得、そして既存顧客のロイヤリティを高めるなど、多くのメリットがあります。
コーポレートサイトやサービスサイトと比較して、「情報を探している段階」のユーザーが訪れやすいという特徴があります。そのため、将来的に顧客になる可能性がある見込み客を育成し、維持するのに役立ちます。
採用サイト
採用サイトは、企業が優秀な人材を獲得するために重要な役割を果たします。
求職者に対して、会社の魅力や雰囲気、仕事内容などを効果的に伝えられます。
採用サイトには、会社概要、事業内容、求める人物像、選考プロセス、福利厚生など、求職者が知りたい情報を分かりやすく掲載しましょう。
また、社員インタビューやオフィス紹介などのコンテンツを通じて、会社の文化や価値観を伝えることができます。採用サイトを通じて、企業と求職者のマッチングを促進し、優秀な人材の確保につなげられるのです。
ECサイト
ECサイトとは、インターネット上で商品やサービスを販売するためのWebサイトです。
オンラインショッピングの普及に伴い、多くの企業がECサイトを運営しています。
ECサイトを制作する際は、ユーザーにとって使いやすく、商品情報が分かりやすく提示されていることが重要です。
また、決済システムやセキュリティ対策にも十分な注意を払う必要があります。ECサイトを通じて、企業は販路拡大が可能となり、ビジネスの成長につながります。
ランディングページ(LP)
ランディングページ(LP)とは、Webサイトの中でも特定の目的を達成するために作られた単一のページです。
主な目的は、広告やキャンペーンから流入したユーザーを効果的に誘導し、コンバージョン(購入、会員登録、資料請求など)を促進することです。
通常、商品の説明や購入ボタンなど多くの情報を含む、縦長の1ページで構成されます。効果的なLPを作成するには、ターゲットユーザーのニーズを的確に捉え、説得力のあるコピーライティングとビジュアルデザインを組み合わせることが重要です。
Web制作の相場
初めてWeb制作を行う場合、どのくらいの金額がかかるのかは気になるのではないでしょうか。
ここでは、サイトの規模ごとに相場感を解説します。
LP(ランディングページ)
ランディングページは、通常1ページのみで構築されるため、制作コストを低く抑えられます。
ページの品質や機能性に応じて価格は異なりますが、概ね5万円からの制作が可能です。
小規模サイト(個人事業主・中小企業向け)
小規模サイトとは、トップページや会社概要、製品やサービスの紹介など、基本的なコンテンツのみで成り立っているサイトのことを言います。
シンプルなデザインで10ページ程度の場合、30万円〜50万円が目安です。
店舗向けサイト
レストラン、エステサロン、美容院などの店舗を紹介するWebサイトを作る際には、制作費だけでなく、店舗やメニューの写真撮影にかかる費用も念頭に置く必要があります。
写真をメインにした10〜15ページのサイト制作では、費用は約40万円から見積もるとよいでしょう。
中規模サイト(中小企業向け)
中規模のWebサイトでは、企業情報の基本的な内容に加え、ニュースリリースやブログのような更新機能があります。
情報量が増加することを考慮し、約30ページ程度のサイトを想定した場合、制作にかかる費用は60万円を超えることが一般的です。
大規模サイト(中堅・大企業向け)
大型Webサイトでは、中型サイトの内容に加え、会員登録や予約システムなどの複雑な機能が必要になります。
ブランドサイトなど60ページを超える場合、制作には500万円以上の費用が一般的です。
ページ数が増えると、それに伴い検証や修正の作業も多くなり、制作コストが高くなります。
大規模サイトでは、システム開発、SEO、セキュリティの強化など、多岐にわたる追加費用が発生するため、CMSの活用などにより運用コストを低減する工夫が求められます。

Web制作を成功させるためのポイント
Webサイトの目的や目標を明確にする
Webサイトの制作を成功させるためには、実作業に入る前や外部への委託を行う前に、次の3つの準備をしておくことが重要です。そのうちの一つがWebサイトの目的や目標を明確にすること。
Webサイトを制作する際、最も重要なことは目的や目標を明確にすることです。Webサイトは、企業の顔となるだけでなく、ビジネスの成功に直結するツールです。明確な目的や目標なしでは、制作の方向性が定まらず、費用や時間を無駄にしてしまう可能性があります。
Webサイトの目的は、企業によって異なります。
・新規顧客の獲得
・ブランドイメージの向上
・商品やサービスの販売
などさまざまな目的が考えられます。目的を明確にすることで、ターゲットとなる顧客層や、伝えるべきメッセージ、必要な機能などが見えてくるでしょう。
また、目標を数値化することも重要です。たとえば、「月間アクセス数を10,000件にする」「問い合わせ件数を月100件にする」など、具体的な数値を設定することで、制作の成果を測定し、改善につなげられます。
Webサイトのターゲットユーザーを設定する
Webサイトのターゲットユーザーを明確に設定することは、Web制作において非常に重要です。
ターゲットユーザーを理解することで、そのユーザーに適した情報構成やデザイン、機能を提供できます。
まず、ユーザーの属性(年齢、性別、職業など)や目的、悩みを洗い出しましょう。
次に、ペルソナを作成し、ターゲットユーザーを具体的にイメージしてください。
ペルソナを基に、ユーザーがWebサイトに求める情報やサービスを考え、それらを提供できるようなサイト設計を行います。ターゲットユーザーを意識することで、ユーザーにとって価値のあるWebサイトを制作できるでしょう。
RFPを作成する
Web制作プロジェクトを成功させるためには、RFP(Request for Proposal)を作成することが不可欠です。
RFPとは、プロジェクトの目的、要件、予算、スケジュールなどを記載した資料のことです。
RFPを適切に作成することで、Web制作会社とのコミュニケーションがスムーズになり、プロジェクトの成功確率が高まります。RFPは、プロジェクトの基盤となる重要な資料のため、十分な時間をかけて作成しましょう。

Web制作依頼ならWebま!へお問い合わせを
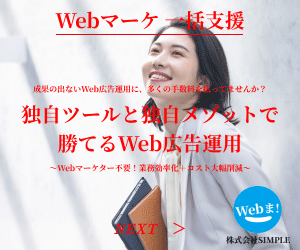
お問い合わせはこちら⇒https://webma.co.jp/
Web制作で押さえておきたい基本用語10選
HTML
HTMLはHyperText Markup Languageの略で、Webページの構造を定義するマークアップ言語です。
HTMLタグを使用して、見出し、段落、リスト、リンク、画像などの要素を配置し、文書の構造を作ります。
CSS
CSSはCascading Style Sheetsの略で、HTMLで作成されたWebページのデザインを指定するための言語です。
文字の色やサイズ、背景色、要素の配置などを設定でき、Webサイトの見た目を自由にカスタマイズできます。
JavaScript
JavaScriptは、Webページに動きや機能を追加するためのプログラミング言語です。
HTMLとCSSで構築されたWebページの構造とデザインに、インタラクティブな要素を加えられます。
たとえば、ボタンクリックに反応したアニメーション、フォームの入力チェック、動的なコンテンツの表示などがJavaScriptで実現されています。
レスポンシブデザイン
デバイスの画面サイズに応じてウェブページのレイアウトが自動的に調整されるデザインのアプローチのことです。
スマートフォン、タブレット、デスクトップなど、異なる画面サイズに対応するために、レイアウトやコンテンツが自動的に調整されます。
これにより、ユーザーはどのデバイスからアクセスしても、読みやすく使いやすいWebサイトを体験できます。
SEO (Search Engine Optimization)
SEOとは、検索エンジン最適化のことです。
Webサイトを検索エンジンでより上位に表示されるように最適化することで、サイトへのアクセス数を増やすことを目的としています。
SEOを効果的に行うことで、検索エンジンからの流入を増やし、サイトの認知度や売上の向上につなげられます。
ただし、SEOは長期的な取り組みが必要であり、検索エンジンのアルゴリズム変更にも対応していく必要があります。
CMS (Content Management System)
CMSとは、Webサイトのコンテンツを管理するシステムのことです。
CMSを利用することで、HTMLやCSSなどの専門知識がなくても、記事の投稿や更新、デザインの変更などが可能です。代表的なCMSとしては、WordPress、Drupal、Joomlaなどがあります。
ドメイン
ドメインとは、Webサイトのアドレスに使用される固有の名称のことです。
「example.com」のように、「.com」や「.jp」などのトップレベルドメイン(TLD)の前に、組織や個人を識別するための文字列が付けられます。
ワイヤーフレーム
ワイヤーフレームとは、Webサイトやアプリケーションの基本的な構造やレイアウトを視覚的に表現した設計図です。
デザインの詳細は省略し、要素の配置や情報の優先順位を明確にすることに重点を置いています。
ワイヤーフレームを作成することで、開発チームとクライアントの間でWebサイトの構成について共通理解を得られます。
サイトマップ
サイトマップとは、Webサイトの全体構成を一覧できる設計図のことです。
サイトに含まれるページの階層構造や関連性を視覚的に表現し、ユーザーがサイト内を円滑に移動できるようナビゲーションの役割を果たします。
また、サイトマップはSEOとしても重要な要素です。
ファーストビュー(FV)
ファーストビューとは、Webサイトを訪問した際に、スクロールせずに見える画面の範囲のことを指します。
訪問者が最初に目にする重要な領域であり、ここでサイトの印象が大きく左右されます。
ファーストビューには、サイトの主要なメッセージやコンセプトを明確に伝え、訪問者の興味を引き付ける工夫が必要です。

HP制作依頼・LP制作依頼・サイト制作依頼ならWebま!へお問い合わせを
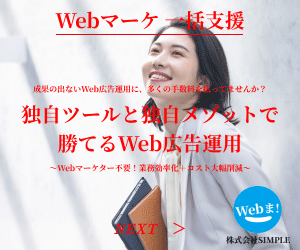
お問い合わせはこちら⇒https://webma.co.jp/

